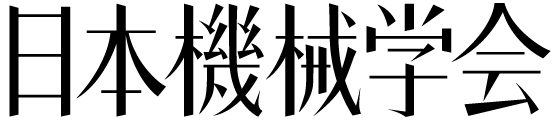部門運営要綱
1.部門の任務
部門協議会に関する規定
昭和52年4月1日制定
平成4年3月3日改定
(部門協議会に移行)
平成6年6月7日改定
2000年12月12日改定
2003年7月1日改定
2006年5月10日改定
2023年12月5日 一部変更
(目的)
第1条 この規定は部門協議会(以下協議会という)に関する事項を定める.
(任務)
第2条 協議会は次の企画運営に関する運営・実施処理に必要な諸般の事項を審議し,かつ会長の諮問に応ずる.
- 所属部門の設置,改廃の立案および各業務分野の割当と調整
- 各部門への行事計画の依頼と調整
- 部門交付金取扱いに関する事項
- 学会の学術活動の検討
- 部門・支部間の行事の調整ならびに相互協力に関する事項
- 他学協会との共同行事の審議
- その他理事会から要請された事項および企画運営上の問題点の検討
(構成)
第3条 協議会の構成は次のとおりとする.
1.議 長 1名 (企画理事兼任)
2.幹 事 1名
3.委 員 各部門の部門長および推進会議(又は専門会議)の運営委員長
(担当副会長・理事) 副会長,財務理事,広報理事各1名
(ただし,これら3名の副会長・理事は協議会の議決には加わらない.)
(幹事)
第4条 幹事は議長が選任する.幹事は議長を補佐する.
(部門運営)
第5条 部門運営に関する通則は別に定める.
(分科会)
第6条 各部門の部門長および推進会議(又は専門会議)の運営委員長は、それぞれ必要に応じ部門および推進会議(又は専門会議)所属の分科会を設けることができる.「分野連携分科会に関する規定」,「部門および専門会議・新分野推進会議所属分科会・研究会に関する規定」は別に定める.
(会合および議事録)
第7条 協議会は必要に応じ会合を開催する.
会合を開催したときは議事録を作成しなければならない.
付 則
この規定の変更は理事会の承認を得なければならない.
部 門 運 営 通 則
昭和62年10月6日制定
2001年12月3日改定
2003年7月24日改定
2004年10月8日改定
2005年5月10日改定
2005年12月13日改定
2006年5月9日改定
2008年12月9日改定
2012年3月27日一部変更(企画理事会承認)
2012年10月3日改定(企画理事会承認)
2014年3月25日改定(企画理事会承認)
2014年10月7日一部変更(企画理事会承認)
2020年3月24日改訂(理事会承認)
2023年12月5日一部変更(理事会承認)
I.基本理念
部門は専門分野の分化に弾力的に対応し,かつ本会活動の機動性を増強し活性化することにより,会員に対し会員個々の興味に応じたきめの細いサービス向上を図る.
II.組 織
1. 登録と構成
本会正員は,関心のある部門を5つまで選択し,第1位~第5位の順位をつけて登録することができる.部門は第1位~第5位の登録会員によって構成する.部門はその規模や目的に応じ、部門評価委員会との協議により以下の3種に区分する.
| (1) | 中・大規模部門(部門M・L) | 直近3年間の研究発表講演会(国際会議を含む)の年平均有料参加者数100名以上 |
| (2) | 小規模部門(部門S1) | 直近3年間の研究発表講演会(国際会議を含む)の年平均有料参加者数100名未満 |
| (3) | 小規模部門(部門S2) | 上記(2)の規模であって,新分野の研究開発を担うもの. |
その運営のため,部門に運営委員会を設置する.
2.役員
(1)役員の定数と任務
部門に次の役員をおく.役員はすべて本会正員とする.
部門長 1名,副部門長 必要に応じて1名,部門幹事 1名,運営委員 10名以上30名以下(部門 S1,S2にあっては運営委員5名以上15名以下)
部門長は部門を代表し,運営委員会を召集するとともに,部門活動を主宰する.副部門長は,部門長がその職務を遂行することが出来ない場合に,その職務を代行する.部門幹事は部門長を補佐して部門の運営を進める.運営委員は運営委員会に出席して審議に参加するとともに,部門活動を推進する.
(2)役員選出方法
1)部門長および副部門長
部門長あるいは次期部門長に就任予定の副部門長は,第4(2)項で定める運営委員会構成員の経験者の中から,第3項で定める代議員,および運営委員会構成員の無記名投票の選挙によって選出する.ただし部門長は第2(3)項規定の任期終了後再選することはできない.
部門長への昇格を前提としない副部門長は,選挙によらず部門長の指名によって決めることができる.
2)部門幹事
正員登録会員の中から部門長が指名する.
3)運営委員
部門長が代議員の中から指名する.ただし,部門長は必要に応じて代議員以外の正員登録会員の中から若干名の委員を指名することができる.
(3)役員の任期
役員の任期はいずれも1~2年とする.
(4)欠員の補充
部門長の指名による役員に欠員が生じた時は,部門長がその後任者を指名することができる.
3.代議員
(1)任務
部門に代議員をおく.代議員は運営委員の候補者になるとともに,部門事業を積極的に支援し,部門長の選挙に加わる.
(2)選出方法
部門長は各支部長に代議員の選出を依頼する.代議員は正員の登録会員でなければならない.
(3)定数
1部門の代議員定数は20名以上,30名以下とする.部門は支部地区に在住する登録会員数(第1位~第5位登録者の合計)を基礎に各支部の代議員数を定める.
(4)任期
代議員の任期は1~2年とする.留任をさまたげないが,原則として4年を限度とする.
4.運営委員会
(1)任務
運営委員会は部門の最高決議機関であり,部門に与えられた権限の範囲内で,部門の運営に関わるすべての事項を審議・決定する.
(2)運営委員会構成員
運営委員会は,部門長,副部門長,部門幹事,運営委員,並びに第5項で定める所属委員会の委員長のうち部門長が指名する若干名のもの,によって構成する.これらの構成員を,運営委員会構成員と称する.
(3)開 催
運営委員会は部門長が運営委員会構成員を召集しこれを開催する.また運営委員会構成員の過半数の要請がある場合には,部門長はこれを開催しなければならない.
ただし,部門長が必要と認めた場合,運営委員会構成員の召集に代わる会議形態をもって,運営委員会開催に代えることができる.以下,このような形態で開催した運営委員会を代行運営委員会と称する.
(4)定足数
運営委員会は運営委員会構成員の過半数の出席をもって成立する.議決は出席者の過半数をもって行うが,代理出席者は定足数および議決に含めない.ただし,代行運営委員会はその会議形態に応じた回答が運営委員会構成員の過半数から得られたことをもって成立し,議決はその回答数の過半数をもって行う.
5.所属委員会
(1)設置と目的
運営委員会は部門活動を効率的に進めるために,必要に応じて各種の所属委員会を設置することができる.委員会の名称および目的は運営委員会で定める.
(2)役員と任務
各所属委員会に次の役員を置く.
委員長 1名 ,副委員長,幹 事 必要に応じて1名,委 員 若干名
委員長は所属委員会を主宰し,運営委員会が必要と認める活動を行うとともに,所属委員会を代表してその活動内容を運営委員会に報告する.副委員長,幹事は委員長を補佐して委員会の活動を進める.委員は委員会活動に参加する.
(3)役員の選出方法
部門長は,正員登録会員の中から所属委員会委員長を指名する.副委員長,幹事および委員は委員長の推薦に基づき,部門長が承認する.
(4)任期
所属委員会委員長の任期は1~2年とする.特別の事情がある場合に限り1回だけ再任できる.副委員長,幹事および委員の任期は委員長の任期に準ずる.
(5)欠員の補充
所属委員会委員長に欠員が生じた時は,部門長がその後任者を指名する.副委員長,幹事および委員に欠員が生じ,補充の必要があるときは,委員長の推薦に基づき,部門長が承認する.
III. 事 業
部門は以下の事業を積極的に実施する.また,会員のために必要と思われるその他の事業についても積極的に企画,実施することができる.
6.集会事業
(1)国際会議を含む研究発表講演会の企画,実施
(2)招待講演会を含む特別講演会の企画,実施
(3)講習会等の啓蒙活動
(4)見学会の企画,実施
7.技術情報提供活動
(1)国内外の研究動向の調査とレビュー紙発行
(2)公的機関からの調査・研究
(3)会誌,論文集の特集号等の企画,並びに記事,論文投稿勧誘
(4)学会基準等の規格関係調査活動,並びに学会の研究推進に関わる活動
8.分科会活動
部門および専門会議・新分野推進会議は,特定テーマにより3年以内の設置期間を定めた分科会を設けることができる.(詳細については,「部門および専門会議・新分野推進会議所属分科会・研究会に関する規定」を参照)
9.研究会活動
部門および専門会議・新分野推進会議は,設置期間を定めない研究会を設けることができる.(詳細については,「部門および専門会議・新分野推進会議所属分科会・研究会に関する規定」を参照)
附 則
本通則の改廃に際しては,理事会の承認を得なければならない.
[参考資料]
新設部門の運営と実施項目
【運 営】
- 1.運営委員会構成
- 原則として新設部門長を含め30名以内で構成する.
- 2.任期
- 部門に準じる.
- 3.新設部門長の選出
- 委員の互選による.
- 4.委員の選出
- 初年度の委員は発起人の中で互選し,次年度からは運営委員会で選出する.
- 5.所属委員会
- 新設部門は必要に応じて所属委員会を設置することができる.
- 6.運営経費
- i ) 学会からの補助金
- ii) 行事収入
【実施できる項目】
(1)行事企画実施
(2)学会内行事等への委員推薦
(3)ニュースレター発行
(4)会報ページ使用
(5)所管理事会からの依頼事項(会誌記事推薦,年次大会企画等)
(6)他団体の賞・助成等への候補者推薦
(7)分科会,研究会の設置
(8)他学会行事への共催
【実施できない項目】
(1)代表会員候補者推薦
(2)部門賞の設置
部門を運営するにあたってのお願い
第69期理事会
2010年7月14日企画理事会改正
2019年1月15日企画理事会改正
2020年3月24日企画理事会改正
1.本会名義使用
理事会の承認を受けてないものが本会の出版物として取り扱われることのないよう注意願います.
2.事業運営にあたって
(1)集会事業
集会事業は,受益者負担の原則のもとに,参加費をもってその運営を行います.そのほかにも教材,講演論文集への広告掲載や,機器展示会を行って参加者の費用負担の軽減を図ることができます.
(2)企業協力集会事業
集会事業を企画するにあたり,会場提供やセッション編成等に対して協力していただける企業がある場合は,別に定める規定によりその支援を依頼することができます.
(3)広告料について
講演論文集,教材,ニュースレター等に広告を掲載する場合は,別に定める料金で行ってください.
3.部門事業経費取扱注意事項
(1)収支出納の取扱い
(i) 収入と支出の出納は全て学会を通して行います.
(ii) 請求・領収書の発行を部門等が直接行うことはできません.
(iii)開催地の実行委員会で出納を行うと決算時に混乱を生じますので,絶対に避けてください.
(2)仮払金
行事開催前に実行委員会が運営資金等を必要とする場合は,予算書に従い学会より当該 委員会に仮払金を支出し,行事終了後一定期間内に領収書を添えて精算していただきます.ただし,会場使用料等多額の支払いについては本会より直接行います.
(3)補助金申請財団等の補助金申請はできますが,会長名で手続きを行いますので,予め理事会に報告し承諾を得てください.
4.集会事業の任務分担について
部門制開始と共に集会事業数が増加し,従来の運営方法では量的に事務局が対応できなくなり,合理化をはかっております.しかしながら,その合理化にも限界があるため,部門運営要綱に添付の任務分担表に記載のように企画の委員にも分担して運営に携わっていただくようになりました.事業企画にあたっては,各項目毎に担当委員を決めてロードの分散・軽減化を図ってください.
メニューへ
一般社団法人 日本機械学会