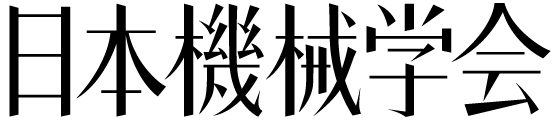関連規定 25
分野連携分科会に関する規定
2023年12月5日 制定(理事会承認)
(目的)
第1条 横断的分野における萌芽的な技術の調査・研究,あるいは既存技術の高度化,体系化などの活動,並びに新たな横断分野のための推進体制の構築を目的とする.
(名称)
第2条 分科会の名称は,「〇〇連携分科会」とする.
(構成)
第3条 分科会の構成は,複数部門からの委員による参加とし,主査1名および幹事,委員をもって構成する.
(設置期間)
第4条 分科会の設置期間は2年とし,延長申請が認められた場合は更に2年,最長6年までとする.
(運営経費)
第5条 分科会の運営経費は,分野連携分科会運営資金からの支出とし,交付額は,分野連携委員会において定める.
(設置手続き)
第6条 分科会の設置手続きは以下のとおりとする.
(1)幹事部門を定め,幹事部門より分野連携委員会委員長宛に申請する.
(2)分野連携委員会委員長は,第6条(1)の申請書を分野連携委員会に諮る.同委員会の審査後,理事会の承認をもって設置する.
(延長手続き)
第7条 分科会の設置延長申請の手続きは以下のとおりとする.
(1)申請書に活動報告と延長後の活動計画を添え,分科会終了3カ月前までに分野連携委員会委員長宛に申請する.
(2)分野連携委員会委員長は,延長申請書を分野連携委員会に諮る.同委員会の審査後,理事会の承認をもって延長できるものとする.
(活動および活動報告)
第8条 分野連携分科会の活動および活動報告は以下のとおりとする.
(1)会議開催,調査・研究活動等全てを自主的に行うものとする.
(2)活動終了時に報告書を分野連携委員会委員長に提出する.
(3)活動期間中および活動終了時に年次大会等でのOSまたは特別企画を実施する.
(4)活動内容を会員に広く周知する.
(部門活動評価とのリンク)
第9条 本分科会の活動を部門活動評価における重点活動項目の重要事項として位置付ける.
(規定の改廃)
第10条 本規定の改廃に際しては,理事会の承認を得るものとする.
付記: 本規定の発効に伴い,以下の規定を廃止する.
・部門協議会直属および部門所属分科会に関する規定
メニューへ
一般社団法人 日本機械学会