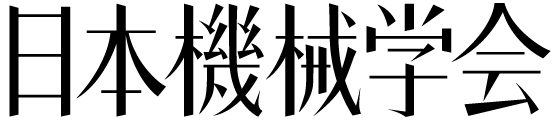No.189 アメリカ滞在記
2020年度編修理事 赤松 史光[大阪大学 教授]
JSME談話室「き・か・い」は、気軽な話題を集めて提供するコラム欄です。本会理事が交代で一年間を通して執筆します。

2020年度(第98期)編修理事
赤松 史光 [大阪大学 教授]
Memories of the Stay in the US
1997年10月から1年間、当時の文部省在外特別研究員として、カリフォルニア大学アーバイン校(University of California at Irvine: UCI)に滞在した際のことを振り返ってみたいと思います。
アーバイン市は、ロサンゼルス市から南西へ約50 kmのところに位置しています。アーバイン市は完全な計画都市で、UCIはアーバイン市が設立される際に誘致されたとのことで、キャンパス内にはショッピングモール、映画館、コンサートホール等の市民のための施設があり、全面芝生のグランド、テニスコート、体育館はいいつでも使用することができました。キャンパスを取り囲むように、学生寮や大学職員の庭付き戸建て住宅、私のような短期滞在の研究員の集合住宅があり、共同の温水プールやジャグジーが自由に利用できました。
UCIでのホストは航空・機械工学科のSamuelsen教授でした。教授は学外でも自分自身の会社を経営されており、多くのスタッフや学生が研究に従事していました。研究室は基本的には教授一人単位で運営されており、スタッフは大学の職員ではなく教授の研究費から給与を得ているので、教授と学生が数名という研究室が大半でしたが、Samuelsen教授の研究室には、秘書4名、技術スタッフ3名、博士研究員3名、博士課程学生6名、修士課程学生4名、学部生8名が在籍していました。アメリカでは卒論・修論研究というものはなく、研究活動を行う全ての学生は教授から給与を得ているので、人件費だけでも毎年数千万円の研究費を必要とすることを考えると、アメリカの大学で研究を行うことの困難さを実感しました。研究内容の詳細については研究室のホームページhttp://www.ucicl.uci.edu/でバーチャルツアーができますので、是非、ご参照下さい。
アメリカの学生は、日本の学生とは異なり入学・卒業時期や年齢やバックグランドも様々です。卒業後もすぐには就職せず、ボランティア活動や外国放浪をしたり、別の学部へ編入する等、自分自身の人生を何事にも縛られることなく自由に生きているように感じました。この要因として、大学周辺に安価な学生寮が完備され、研究活動により給与が得られるために、学生時代に親から独立できることもありますが、個人の長所を最大限に生かし個性を重んじるアメリカの教育システムによるところも大きいと感じました、アメリカでは人とは違って自分にしかできない経験や特技を身につけることこそが重要で、真に社会がそのような人を欲していることを実感できました。
実際、アメリカの人たちはよく転職します。研究室のスタッフも様々な経歴を持っており、雇用契約も年単位で行われていました。話を聞いてみると、今よりもいい条件の職場があればすぐにでも転職すると言っておられました。これは、アメリカ人が未知の大地に移民してきた根っからのチャレンジャーであることが大きな要因であると思います。アメリカでは大学の研究機関で働くということは、非常に名誉なことであると考えられており、スタッフは自身の仕事に誇りをもっておられました。これも前述したように、大学が地域社会の一部にとけ込んで密接な関わりを持っていることに起因していると思います。
アメリカ滞在の最大の思い出は、アメリカ合衆国本土の最高峰 標高4418 mのMt. Whitneyに登頂したことです。研究室の同僚のTrevorの手配により、登山の許可を事前に得てもらいました。麓のLong Pineという街に車をとめ、車中で一晩を過ごし午前4時に起床して、延々午後2時まで10時間歩き続けて、やっとの思いで頂上に着きました。富士山の登山道のように比較的整備された決まったルートはなく、途中には絶壁のような雪原を登山靴にクランパンを装着して登らなくてはならない箇所や、遙か下方に転落しかねない岩場を通らなくてはならないのです。苦労した甲斐あって、頂上にたどり着いた瞬間には、何とも言葉では表しようのない感動がこみ上げてきました(写真1)。しかし、登頂に成功した達成感でこの時点では十分認識できていなかったのですが、今来た道のりを同じ分だけ引き返す必要があったのです。Trevorは普段から体を鍛えているだけあり小走りするように下山していました。一方私の方は運動不足がたたり全くペースがあがりません。彼は私より先に降りては、途中で待っていてくれるのですが、私がやっとの思いで彼の待つ所へ到着すると、”大丈夫?”と聞いてはくれるのですが、私が普段日本人と接する時と同じように、本当は休みたくても”大丈夫!”と答えると、それをそのままそれを信じてくれて、私は休むことなく下山することになりました。このときほど、Yes, Noをハッキリ言わなくてはならないと実感したことはありません。結局、麓のLong Pineについた頃には午後10時をまわっていました(写真2)。もう少し遅くなっていれば道に迷っていたかと思うと、下山中には少々閉口していたにも関わらず、Trevorの速い下山ペースに心から感謝しました。

写真1 山頂にある登頂記念プレート

写真2 ようやく麓までたどり着いて一安心
別の機会には、ラフティングというゴムボートでの急流の川下りにチャレンジしたのですが、一切の責任は自分で負うという内容の誓約書にサインしさえすれば、私のような全くの素人でも、Mt. Whitneyの登山許可と同様に簡単に許可が出ます。日本では考えられないような激流の中を、川べりのごつごつした岩すれすれにゴムボートが進んでいき、船の操作を一歩誤れば水中に投げ出され、岩に体をぶつけて大けがをするのは確実です。Mt. Whitneyの登山許可といい、ラフティングといい、自己責任を明確にすれば何でもすることができる、まさに”自由の国アメリカ”を実感しました。
日本へ帰国して22年以上の時が経過しましたが、あらためて振り返ると、日本に居たのでは決して体験することのできない多くの貴重な機会を得ることができました。このような機会を与えていただいた関係各位に感謝の念を新たにしています。今後、新型コロナウィルスの問題が収束して、また海外から日本を見つめる機会が早く来ることを祈念しています。